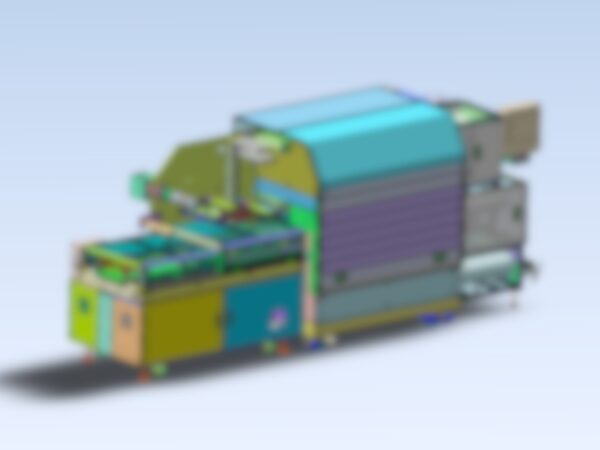CASE 食品粘度測定器
構想設計
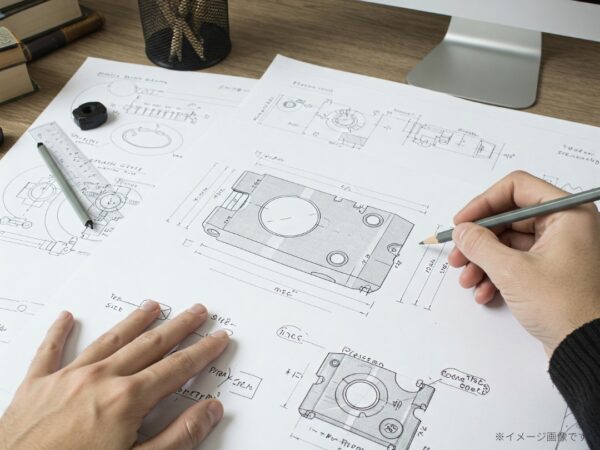
当社HP経由にてお客様よりご相談を頂いた事例で、「食品の粘度測定器」設計・製造のご依頼でした。お客様は食品油の開発をされている部署の方でしたが、エンドユーザーへアピール(営業)する際にわかりやすいデータとして提示するための油特性検出用「粘度測定器」をご検討されておられました。既製品でも類似のものがあるものの、機能的ではあれど見た目が業務用といった印象で、シンプルかつ機能的な測定器をご希望でした。また、先方で特許を取得したいという意向もあり、設計からスタートするに至りました。
お客様より測定に使用するトルク測定器のご指定があり、内部の構造に関しましてマンガ絵のご提供をいただきました。
当社ではお客様の構想案と、別機構での2パターン、構想見積りを検討・作成し、お客様へ提示させていただきました。測定対象物の重量に粘度、負荷検出用のパドル形状等様々な情報を加味し、それぞれの特徴を精査し、お客様と設計方針を相談させていただきました。結果として、お客様よりいただいておりましたマンガ絵を基にした設計案での開発スタートが決定いたしました。
要素検討/試験

構想設計で設計方針は確定したものの、世の中に無い仕組みでの開発となりましたため、要素検討及び試験工程に十分な時間と工数をかける必要がございました。通常であれば最低限の治具やサンプルを使用して試験を行うのですが、今回は構成部品やユニットの組み合わせで取得できるデータへの影響が大きくなる懸念がございましたため、代替実験ではなく完成品に近い「試験機」を作成し、データ採取時の環境を実稼働に可能な限り近づけることで取得データの精度を高く保持することを優先いたしました。
方法としては測定対象物である食品に食品油(①粘度高と②粘度低の2パターン)を定量添加し、測定機に投入後実際にデータを取得。前文の試験を一定n数繰り返し、データの評価を行います。お客様ともこまめにデータおよび意見のやり取りを行い、お客様のご要望に合わせABテストを繰り返し、①②の油で安定してデータ差分が検出できるように調整を行いました。
基本設計
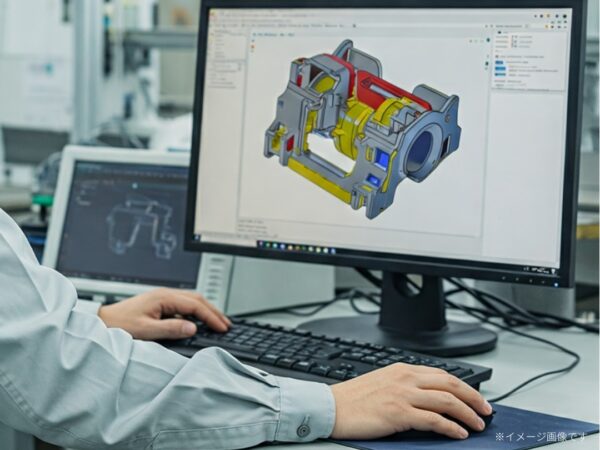
要素検討・試験と同時並行となりましたが、取得データの精度向上のため、本番機に限りなく近い試験機をまずは設計・製造することとなりました。この試験機を活用して要素試験を行うため、構造に多少のカスタマイズ性を残しつつ、容器やパドル・電気設計等を網羅した設計を実行いたしました。
また、試験結果に伴い微修正を多く行ったのですが、ソフト(制御系)・ハード(メカ)両方向からの設計変更を繰り返し、要求性能に至るまでトライアンドエラーを繰り返しました。通常の装置設計とは全く違う進め方でございましたが、新技術開発として理論・実証のサイクルを回し続けた結果、試験機で目標としていた性能を実現するに至りました。
また、本番機の設計は詳細設計になるのですが、トルクドライバーからトルク測定器に変更した場合の数値揺れに備え、基本設計段階でモーター制御に関しても実験を行っておりました。ですが実際に本番機を稼働してみた結果、設計段階ではわからなかった差分減少要因がここにあったようで、再選定をすることとなります。詳しくは詳細設計をご覧ください。
詳細設計
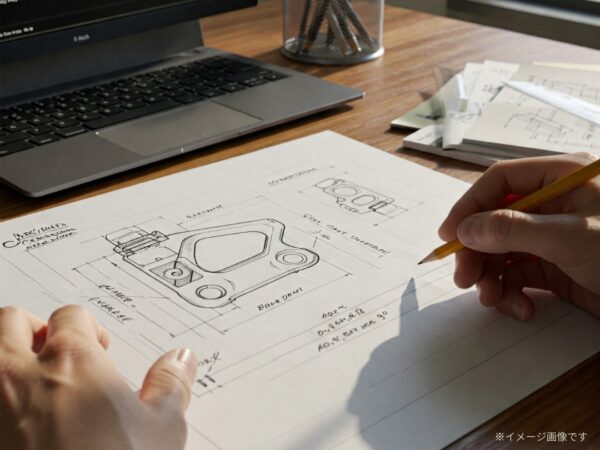
要素試験・基本設計を同時進行で行い試験機の評価に時間をかけたため、本番機設計の段階でおおよその筋道はすでに出来上がっておりました。試験結果から食品攪拌用のパドル形状変更や、微量なトルク差分のソフト面を含めた再現性の高い測定方法の確立も行いました。ですが本番機での稼働をしたところ差分の減少やデータの安定性の低減が確認され、再度調整箇所の把握及び対策(設計変更)を行うこととなりました。
差分減少の原因は唯一試験機と大きく変わったトルク測定器でした。トルクドライバーがモーターの回転力を攪拌用パドルに効率的に伝達していたのに対し、トルク測定器は回転時にクッションになるような挙動ができず、モーターの回転力が効率よく伝達できない事象が確認されたのです。当社はステッピングモーターに光明を見出し、モーターを切り替えた結果、多少の微調整は行った物の試験機同様のトルク差分を安定的に取得できるようになりました。
納品時には当社が確立した測定方法や測定器の制御ソフトの使用手順書等必要な書類と合わせお客様へお渡しし、案件のクローズをさせていただきました。